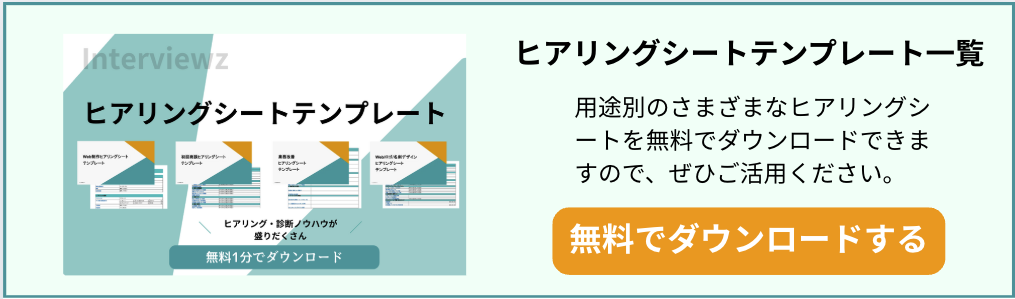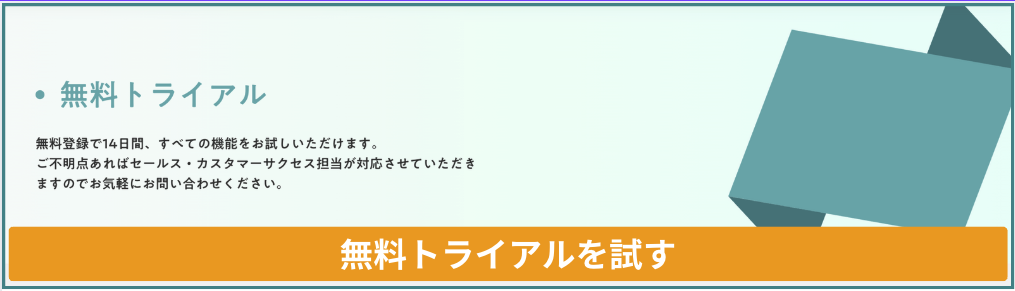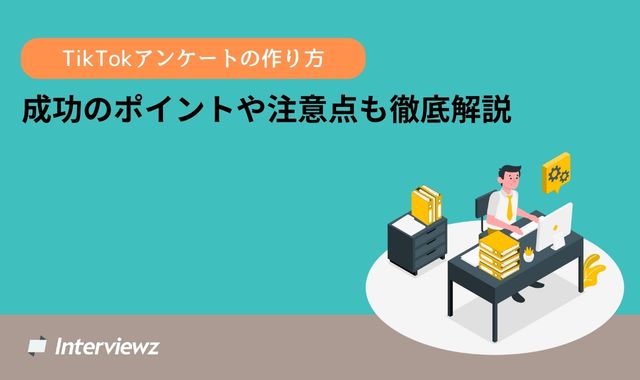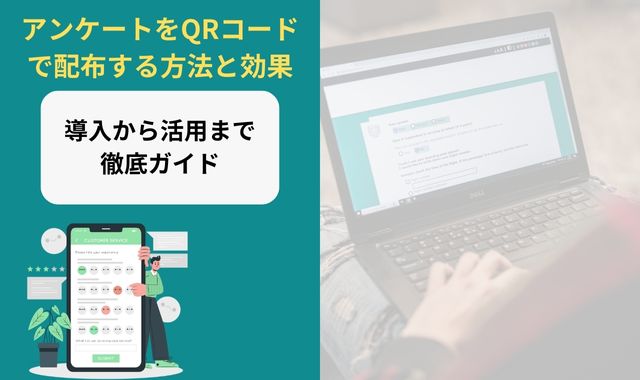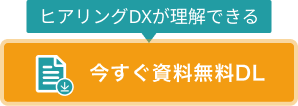ユーザーインタビューとは?主な目的と重要性、設計から進め方を徹底解説
- 2025/07/25
- 2025/07/26

目次
ユーザーインタビューは、サービスや製品の改善に欠かせない調査手法として活用されている手法です。
ユーザーインタビューを実施することで、アンケートなどの定量調査では見えにくい、ユーザー自身も気付いていない本音や課題を深く掘り下げることができるため、より的確なニーズ把握やUI/UX改善に直結する情報が得られます。
しかし、目的や設計を誤ると、得られる情報の質や活用度が大きく変わるため、正しい進め方を理解することが重要です。
そこで今回は、ユーザーインタビューとは何か、主な目的と重要性、設計から進め方を徹底解説します。ぜひ参考にしてください。
ユーザーインタビューとは?基本概要と重要性

ユーザーインタビューの定義と特徴
ユーザーインタビューとは、商品やサービスを実際に利用しているユーザーや、想定ユーザーに対して直接質問し、意見や体験を聞き取るリサーチ手法です。
アンケートのような数値データを集める「定量調査」と異なり、ユーザーの行動や思考、課題感など“なぜ”に迫る深い情報を得る「定性調査」に分類されます。
主に「構造化」「半構造化」「非構造化」の3つのインタビュー形式があり、目的や状況に応じて使い分けます。
定量調査と定性調査の違い
定量調査とは、アンケートやアクセス解析などで数値や傾向を把握し、全体像や統計的な裏付けを得る手法です。
一方、定性調査(ユーザーインタビューなど)では、個々の体験や意見を深く掘り下げ、数字では見えない本質的なニーズや課題を明らかにします。
|
項目 |
定量調査 |
定性調査(ユーザーインタビュー) |
|
データ形式 |
数値・割合 |
言語・エピソード・感情 |
|
目的 |
傾向把握・比較・裏付け |
背景理解・深掘り・仮説生成 |
|
サンプル数 |
多い(数十~数千) |
少数(数名~十数名) |
|
強み |
客観性・再現性 |
本音把握・潜在ニーズ発見 |
ユーザーインタビューが必要な理由
ユーザーインタビューは、ユーザー自身も気づいていない潜在的なニーズや課題の発見に不可欠です。
数値データだけでは見えない「なぜその行動を取ったのか」「どんな背景や感情があるのか」といった本質的なインサイトを得られます。
新規事業のアイデア検証や既存サービスの改善、マーケティング施策の見直しなど、ユーザー中心の意思決定や仮説検証に直結します。
ビジネスへのメリットと期待できる効果
ユーザーインタビューがビジネスに与えるメリットと効果には、以下のようなものが挙げられます。
- ユーザー体験の向上:実際の声をもとにサービスやUI/UXを改善できる。
- 新商品・サービス開発の精度向上:ニーズや課題を的確に把握し、失敗リスクを減らせる。
- 施策の仮説検証・方向性の明確化:アイデアの妥当性を早期に見極め、無駄な投資を防ぐ。
- 顧客満足度やロイヤルティ向上:ユーザー視点の施策が信頼や満足度アップにつながる。
上記のように、ユーザーインタビューは、数字では捉えきれない「本当の顧客理解」と、ビジネス成果に直結する施策立案のために不可欠なリサーチ手法です。
ユーザーインタビューの主な目的と活用場面

新規事業・サービス開発での活用
ユーザーインタビューは、新規事業やサービスの立ち上げ時にターゲット層の潜在的な課題やニーズを把握し、ビジネスアイデアの妥当性や市場性を検証するために非常に有効です。
初期段階では「探索型インタビュー」として、ユーザーの生活や行動背景を深掘りし、想定外の課題や新たな価値観を発見できます。
既存サービスの改善・最適化
既存サービスのリニューアルや機能追加の際には、ユーザーの利用実態や不満点、改善要望を直接ヒアリングすることで、具体的な改善策や優先順位を明確にできます。
インタビューで得た声をもとに、UIや機能の見直し、サポート体制の強化など、ユーザー体験の最適化に直結した施策立案が可能です。
顧客のニーズ把握とペルソナ設定
ユーザーインタビューは、顧客のリアルな行動や思考、価値観を深く理解し、精度の高いペルソナ(理想的な顧客像)を設定する際に不可欠です。
インタビューから得た具体的なエピソードや課題をもとに、カスタマージャーニーやターゲット層の明確化が実現します。
競合調査と市場分析
競合サービスの利用経験や他社との比較ポイントをユーザーに直接聞くことで、自社サービスの強み・弱みや市場におけるポジショニングを把握できます。
定量調査では見えにくい、ユーザー視点での競合評価や選定理由を明らかにできるのも大きな利点です。
UXデザイン・UI改善への活用
ユーザーインタビューは、実際の利用シーンや困りごと、感情の動きなどを可視化し、UX(ユーザー体験)やUI(画面設計)の改善に直結するインサイトを得る手段です。
表情や仕草、言葉の裏にある本音を探ることで、より使いやすく満足度の高いサービス設計が可能となります。
上記のように、ユーザーインタビューは、新規事業開発・既存サービス改善・ペルソナ設定・競合調査・UX/UI改善などのビジネスのあらゆるフェーズで「ユーザー中心」の意思決定を支える強力な手法です。定量調査では得られない深いインサイトが、実践的な施策や競争力強化につながります。
ユーザーインタビューの種類と手法

構造化インタビュー vs 非構造化インタビュー
以下ではまず、構造化インタビューと非構造化インタビューを比較します。
|
種類 |
特徴・メリット |
適用場面 |
|
構造化 |
あらかじめ決めた質問リストに従い一問一答形式で進行します。 全員に同じ質問を同じ順序で聞くため、一貫性と比較性が高いのが特徴です。 短時間で多人数調査や統計分析に向きますが、深掘りはしにくい手法です。 |
大規模調査・傾向把握・定量的分析 |
|
非構造化 |
質問項目はほとんど決めず、テーマだけを設定し自由な対話で進めるのが特徴です。 ユーザーの思考や感情、予想外のアイデアを引き出しやすいですが、話が脱線しやすく分析に時間がかかる手法です。 |
新規アイデア探索・深い洞察 |
半構造化インタビューの特徴とメリット
半構造型インタビューは、基本的な質問指針を持ちつつ、回答に合わせて柔軟に深掘り質問を展開できるのが最大の特徴です。
事前に聞きたいことを押さえつつ、ユーザーの発言や背景に応じて臨機応変に掘り下げられるため、定量的な比較と定性的な深掘りの両立が可能です。
新しい気づきやインサイトを得やすく、実務で最もよく使われる手法ですが、インタビュアーのスキルによって得られる情報の質に差が出やすいため、実施の際は十分注意しましょう。
対面形式とリモート形式の違い
以下では、対面式とリモート形式のインタビューの特徴を比較します。
|
形式 |
特徴・メリット |
注意点・デメリット |
|
対面 |
表情やしぐさなど非言語情報も観察できるのが特徴で、信頼関係が築きやすいのがメリットです。 |
移動や場所の確保が必要となります。 |
|
リモート |
場所や時間の制約が少なく、全国・海外の対象者にも実施しやすいのが特徴です。録画や記録も簡単にできるメリットがあります。 |
通信環境や操作トラブルのリスクがあります。 |
個人インタビューとグループインタビュー
個人インタビュー(デプスインタビュー)は、1対1でじっくり深掘りし、本音や詳細な体験談を引き出しやすいのが特徴です。プライベートな話題や感情面の掘り下げに最適な手法です。
一方、グループインタビュー(フォーカスグループ)は、5~6人程度の少人数グループで座談会形式で実施します。多様な意見や相互作用から新たな気づきを得やすいのが特徴です。ただし、他者の意見に引っ張られやすい面もあるため、注意が必要です。
エスノグラフィー調査との組み合わせ
エスノグラフィー調査とは、ユーザーの生活や行動を現場で観察・記録する調査手法です。
インタビューと組み合わせることで、「言葉」と「実際の行動」のギャップや、ユーザー自身も気づいていない習慣・課題を発見できます。
例えば、日常の使い方を観察した後にインタビューを行うことで、よりリアルなインサイトが得られるでしょう。
上記のように、ユーザーインタビューは、目的や状況に応じて「構造化・半構造化・非構造化」「個人・グループ」「対面・リモート」など多様な手法を選択できます。エスノグラフィー調査と組み合わせることで、言葉だけでなく実行動からも深い顧客理解が可能です。
▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。
- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」
- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」
- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」
- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」
下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。
さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。
効果的なユーザーインタビューの設計方法

目的設定と課題の明確化
ユーザーインタビュー設計の第一歩は、「何を明らかにしたいのか」「どの課題を解決したいのか」など、具体的なゴールを明確にすることです。
例えば「新機能Aの使い勝手に関する課題を特定し、改善案を導く」など、調査の成果イメージまでチームで共有しておくと、インタビューの方向性がぶれません。
インタビュー対象者の選定基準
調査目的に合致したユーザー属性(例:直近3ヶ月以内に利用、週1回以上使用、20代女性など)を明確な条件で定義し、バランスよく選定しましょう。
異なる利用頻度や目的を持つユーザーを含めることで、多角的な視点や課題を発見しやすくなります。
リクルーティング方法とアポイントメント
対象者には謝礼や所要時間、実施方法(対面・オンライン)を明確に伝え、協力しやすい環境を整えます。
リクルーティング時は、条件に合う参加者をWebフォームやアンケートで絞り込み、アポイントメント時に複数の候補日を提示して調整しましょう。
質問項目の設計とテンプレート作成
質問はオープンエンド型(自由に答えられる形式)を中心に設計し、ユーザーのストーリーや背景を引き出せる内容にします。
質問の流れ例は以下の通りです。
- 利用前の悩みや課題
- 興味を持った背景や期待
- 情報収集・比較のポイント
- 実際に使った感想や成果
- 補足質問・まとめ
質問リストや進行表を事前にシート化しておくと、当日の進行がスムーズです。
時間配分と進行シナリオの構築
インタビュー全体の所要時間を決め、各質問ごとの目安時間を設定しましょう。
最初はアイスブレイクや自己紹介から入り、徐々に本題へと進めるシナリオを作ると、参加者がリラックスして本音を話しやすくなります。
質問の順序や切り替えタイミングも事前にシミュレーションしておくと安心です。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
ユーザーインタビューの実施手順と進め方

事前準備と環境設定
ユーザーインタビューの成功は、事前準備と環境設定がポイントです。
目的や課題を明確にし、対象者の選定・リクルーティング、質問項目や進行シナリオを事前にまとめておきましょう。
オンラインなら通信環境やツール(Zoom等)の動作確認、対面なら静かな場所や録音機材の準備も重要です。
アイスブレイクと関係構築
開始直後は、自己紹介や相手のプロフィール確認、雑談などで緊張をほぐし、安心して話してもらえる雰囲気を作ります。
いきなり本題に入らず、相手のバックグラウンドや最近の出来事などから会話を始めると、信頼関係が築きやすくなります。
質問テクニックとヒアリングのコツ
質問テクニックとヒアリングのコツは以下のとおりです。
- オープンエンド型の質問(「どのように感じましたか?」など)で自由に話してもらう。
- 回答を誘導しない・評価しない姿勢を徹底し、傾聴を心がける。
- 「なぜ?」を連発せず、「どんなことを期待しましたか?」などストーリーを引き出す言い換えを使う。
- ユーザーの行動や感情の流れを丁寧に聞き取る。
深掘り質問と仮説検証の方法
回答の背景や理由をさらに掘り下げるため、「もう少し詳しく教えていただけますか?」など追加質問で深掘りしましょう。
また、仮説がある場合には、「〇〇の場面ではどんなことがありましたか?」と具体的な状況を聞いて検証します。
ただし、ユーザーの言葉を否定せず、あくまで自然な流れで深掘りすることが大切です。
インタビュー中の記録と観察ポイント
録音・録画、メモを活用し、発言内容だけでなく表情やしぐさ、間の取り方など非言語情報も観察しましょう。気になった点や新たな気づきはその場でメモし、後で分析しやすいよう整理します。
1人が質問、もう1人が記録担当になると、より正確な記録が可能です。
質問設計のコツと避けるべきNG例

オープンエンド質問の活用法
ユーザーインタビューでは、オープンエンド型の質問(自由に答えられる質問)を優先しましょう。
例えば「このサービスを使ってどう感じましたか?」「どんな場面で困りましたか?」など、Yes/Noで終わらず、ユーザーの体験や考えを広く引き出せます。
具体的な行動を引き出す質問文例
抽象的な質問よりも、過去の具体的な行動や経験に焦点を当てた質問が効果的です。
例えば、以下のような質問です。
- 「直近でこのサービスを使ったとき、最初に何をしましたか?」
- 「購入を決めたとき、どんな情報を参考にしましたか?」
- 「利用前にどんな悩みがありましたか?」
上記のような質問は、ユーザーの実際の意思決定や行動プロセスを明らかにします。
誘導質問を避ける方法
「〇〇が便利でしたよね?」のような誘導的な聞き方は避け、ニュートラルな表現を心がけましょう。
例えば「この機能はどうでしたか?」と聞くことで、ユーザー自身の意見を引き出せます。
また、正解・不正解はないことを事前に伝え、自由に話してもらう雰囲気作りも重要です。
「なぜ」を多用しない質問テクニック
「なぜ?」を繰り返すと尋問のように感じられ、ユーザーが答えづらくなります。
「どんなきっかけでそう思いましたか?」「そのとき、どんなことを考えていましたか?」など、理由や背景を自然に引き出す言い換えを使いましょう。
仮説検証に効果的な質問パターン
仮説検証に効果的な質問パターンには、以下のようなものが挙げられます。
- 「〇〇の場面では、どんな行動を取りましたか?」
- 「そのとき、どんな課題を感じましたか?」
- 「他のサービスと比べて、違いを感じた点はありますか?」
このように、仮説に対してユーザーの実体験を具体的に尋ねることで、検証の精度が高まります。
避けるべきNG例
インタビューで避けるべきNGな質問には、次のようなものが挙げられます。
- 誘導質問:「この機能、便利でしたよね?」
- クローズド質問:「このサービスは好きですか?」
- 抽象的すぎる質問:「どう思いますか?」
- 「なぜ?」の連発:「なぜそうしたのですか?なぜですか?」
インタビューでは、つい上記のような質問をしがちです。くれぐれも注意しましょう。
▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しいます。
アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。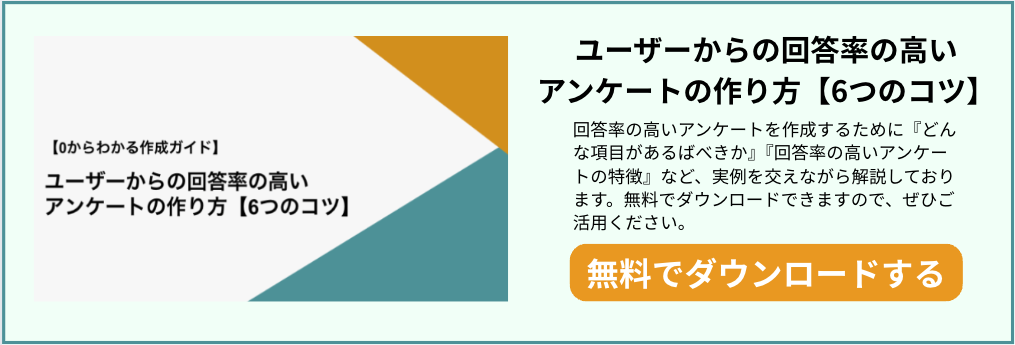
インタビュー結果の分析と活用方法

データ整理と分析手法
インタビュー後は、発言内容を文字起こしし、ポストイットやシートに書き出して整理しましょう。
次に、KJ法やコーディング(内容ごとにラベル付け)を用いて、似た内容をグループ化・分類します。
KJ法では、グループごとにタイトルを付け、時系列やプロセスに沿って並べることで、顧客体験の流れや課題を可視化できます。
インサイトの抽出とパターン発見
グルーピングしたデータから、共通する課題・ニーズ・感情を抽出し、複数のユーザーに共通するパターンや特徴を見つけます。
少数意見でも強いインパクトや新規性があれば、重要なインサイトとして取り上げることが大切です。
AIやChatGPTを活用すれば、発言要約や上位下位分析を効率的に進められるでしょう。
ペルソナ作成と顧客理解の深化
抽出したインサイトやパターンをもとに、代表的な顧客像(ペルソナ)を具体的に作成しましょう。
年齢、職業、価値観、行動パターンなどを盛り込み、顧客のリアルなプロフィールやカスタマージャーニーを明確化することで、より深い顧客理解が得られます。
改善施策への落とし込み
分析で見えた課題やニーズをもとに、どのような改善策が必要かを具体的に検討します。
優先順位をつけ、実現可能なアクションプランに落とし込むことで、調査結果を実際のサービス改善や新規施策に直結させることが可能です。
チーム内での共有とアクションプラン
分析結果やペルソナ、インサイトはチームや関係者と共有し、共通認識を持つことが重要です。図やマップ、サマリー資料などを活用し、誰でも理解しやすい形でまとめましょう。
その上で、具体的なアクションプランやロードマップを策定し、実行に移します。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。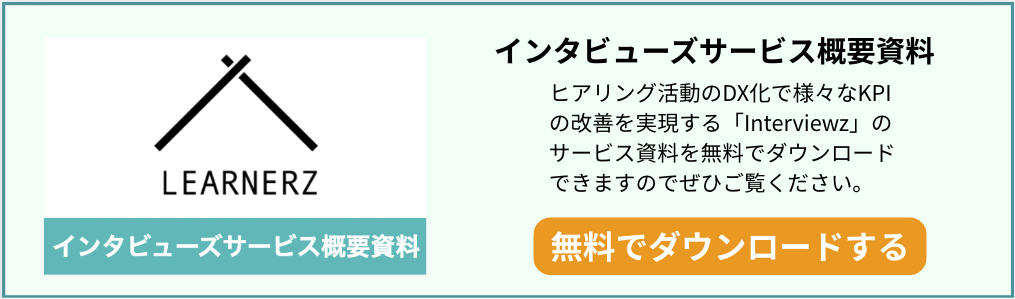
ユーザーリサーチにはインタビューズのヒアリングツールがおすすめ!
インタビューズのヒアリングツールは、ユーザーリサーチを効率化したい企業に最適です。
Web上から直感的にアンケートやインタビュー調査ができ、QRコードやURL、SNSなど多様なチャネルで簡単に回答を集められます。そして、集まったデータは自動で集計・グラフ化され、リアルタイムで分析や共有が可能です。これにより、ユーザーのニーズや課題を迅速かつ正確に把握し、製品やサービスの改善、マーケティング戦略の最適化に直結します。
また、紙や手作業に比べてコストと時間を大幅に削減できる点も大きなメリットです。ヒアリング内容の最適化やKPI改善にも寄与し、ユーザーリサーチの成果を最大化します。
インタビューズのヒアリングツールは、アンケート調査の分析や効率化に最適です。また、インタビューズでは、14日間の無料トライアル期間でも全ての機能を利用可能ですので、ぜひこの機会にお試しください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。