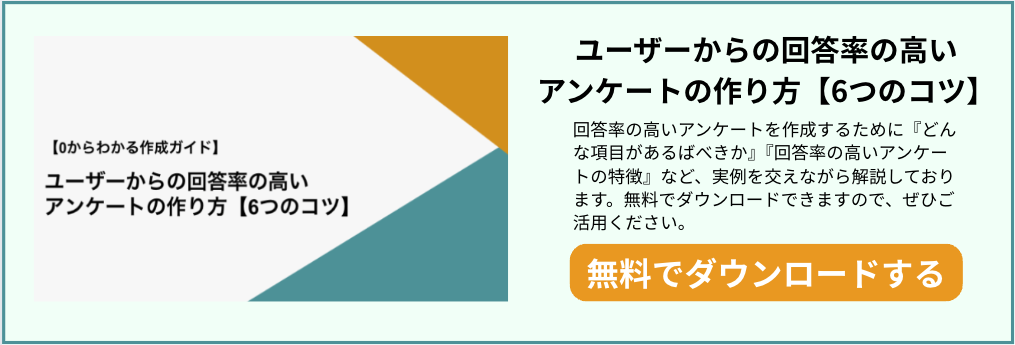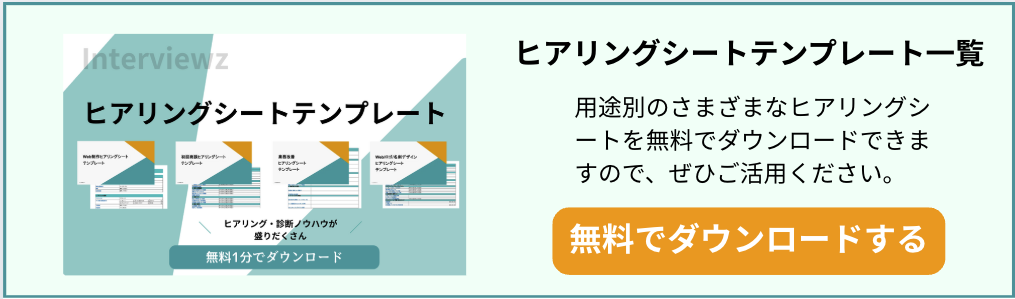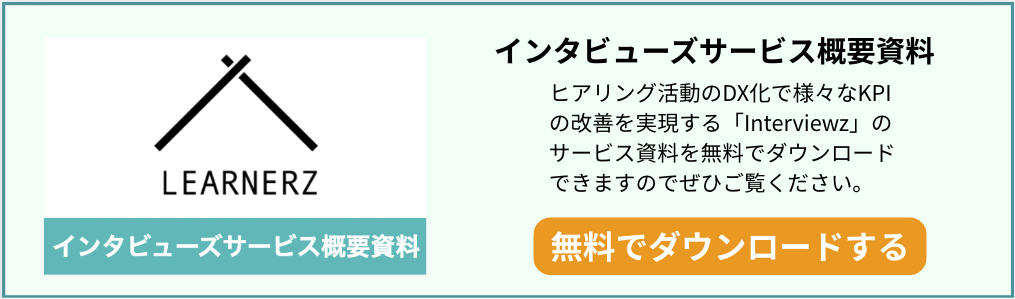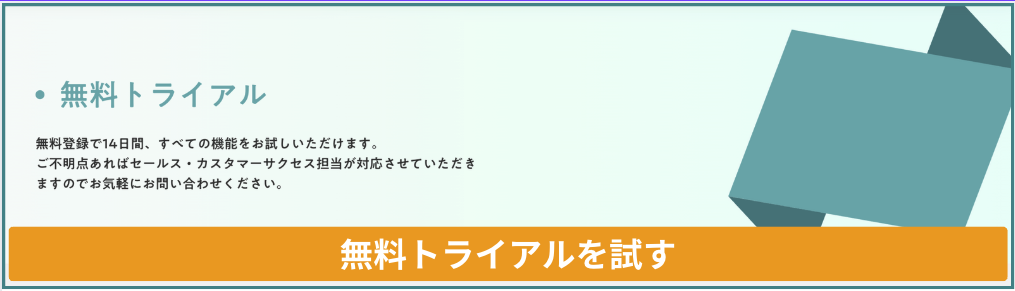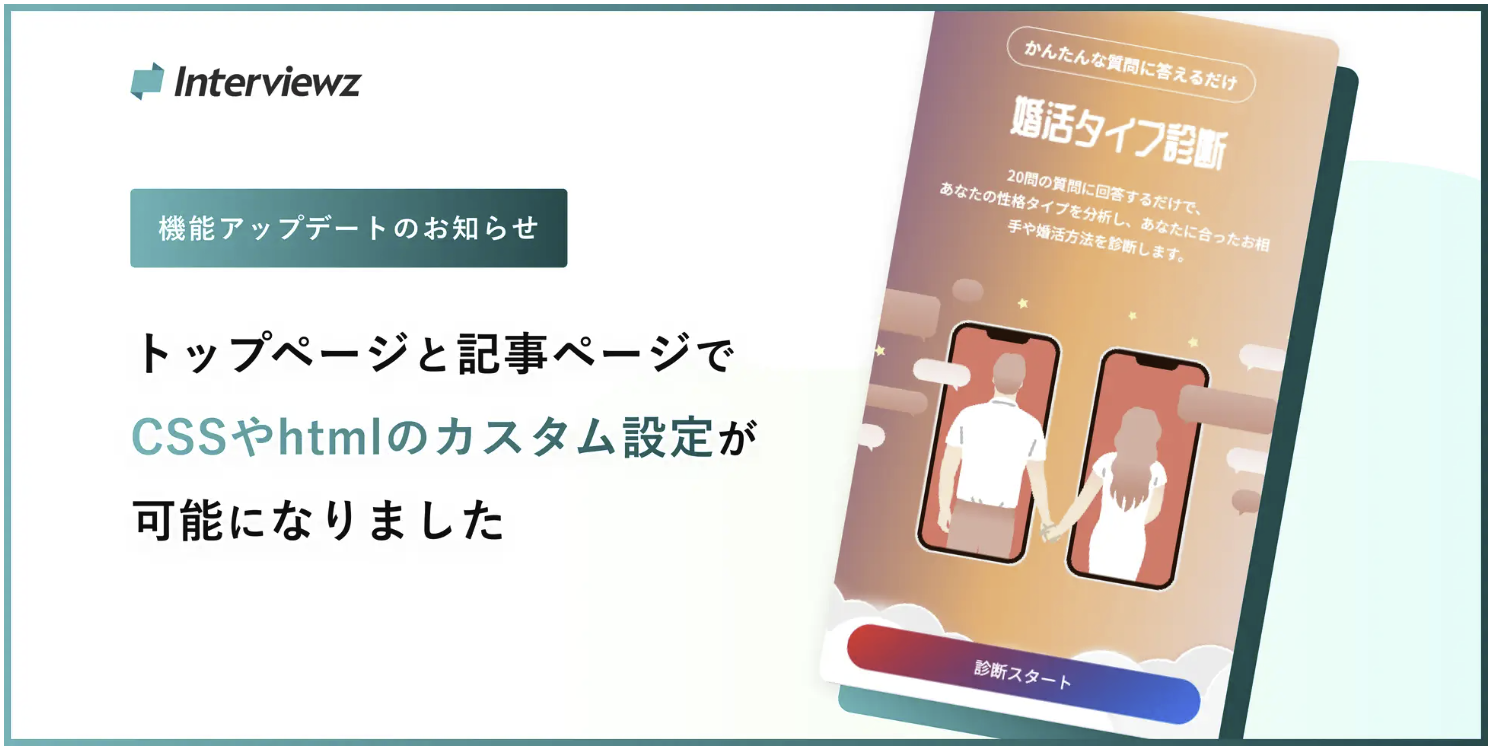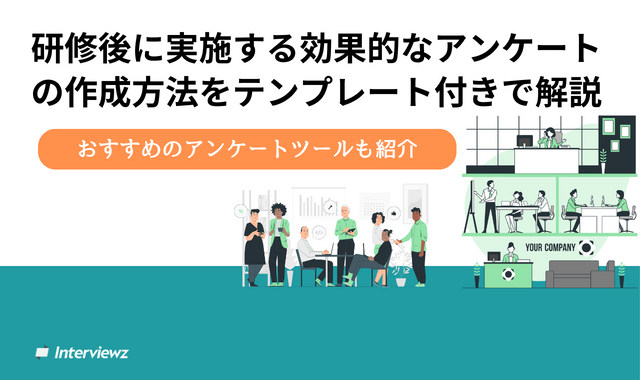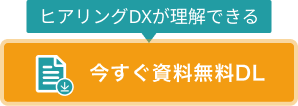定量調査と定性調査の違いとは?使い分け方やメリット・デメリットも解説
- 2024/09/17
- 2025/10/31
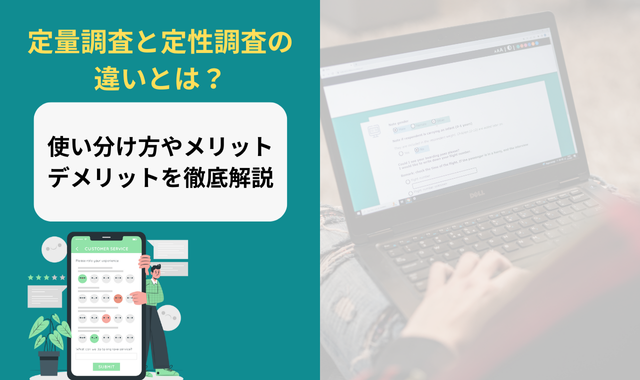
目次
ビジネスの成功には、正確なデータ分析が欠かせません。そのためには、定量調査と定性調査の違いを理解し、適切に使い分けることが重要です。
定量調査は数値データを基にした分析で、具体的な傾向やパターンを把握するのに適しています。一方、定性調査は人々の意見や感情を深掘りし、より詳細な洞察を得るために用いられます。
また、両者のメリット・デメリットを知ることは、より効果的な調査を実施するための重要な要素です。
そこで今回は、定量調査と定性調査の違いと使い分け方、メリット・デメリットを徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。
定量調査と定性調査の基礎知識

定量調査の特徴と目的
定量調査とは、数値データを収集し統計的に分析する調査手法です。
アンケートのように「はい/いいえ」や選択肢で回答を得て、多数のサンプルから市場の傾向や消費者の意見を客観的に把握します。
定量調査の主な目的は、仮説の検証や商品の認知度、購入率、満足度などを具体的な数値で明確にすることです。
これにより、マーケティング戦略や商品開発の根拠となるデータが得られ、効果測定にも利用されます。
定性調査の特徴と目的
定性調査は、数値化できない感情や価値観、行動の理由を深く掘り下げる調査手法です。
少人数の対象者に対面やインタビュー形式で質問し、消費者の心理や購入動機、商品の使用状況など、質的な情報を詳しく引き出します。
定性調査は新たなニーズの発見や改善点の把握、仮説の構築に役立ち、数値では見えない顧客の本音や潜在的な意見を理解する目的で実施されます。
調査データの種類と収集方法
調査データは、大きく分けて「定量データ」と「定性データ」に分類されます。
定量データは数量的で、アンケートやオンライン調査で多数の回答を集め統計分析するのが基本です。一方、定性データは言葉や感情など質的情報で、インタビューやグループディスカッション、観察など直接対話や観察を通じて収集します。
各データを目的に応じて組み合わせることと、適切な調査の設計が成功するための重要なポイントです。
▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しています。
アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。
定量調査のメリットとデメリット

大規模データの収集と統計分析が可能
定量調査では、多くの対象者から数値データを収集でき、統計学に基づく分析が可能です。
これにより、市場の全体傾向や顧客の分布を把握しやすくなり、データに基づいた客観的な意思決定が推進されます。
オンラインアンケートといった効率的な手法を使えば、短期間かつ低コストで大規模なデータ収集が実現可能です。
客観性の高さと深い洞察の難しさ
数値化されたデータは客観的で説得力がありますが、設問設計の影響を受けやすく、回答理由などの深い背景理解は難しい点がデメリットです。
誤った質問設計は信頼性を損なうこともあるため、分析には統計知識や専門スキルが必要です。
さらに、大規模なサンプルの確保にコストや時間がかかることも考慮すべきポイントです。
活用事例と効果
定量調査は、商品の認知度調査や顧客満足度測定、購買行動のパターン解析などに広く活用されています。
マーケティング戦略の効果検証や新製品開発の市場予測に役立ち、数値で示せるため、社内外の関係者への説明や意思決定の説得材料としても強力な効果を発揮します。
▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。
- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」
- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」
- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」
- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」
下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。
さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。
無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
定性調査のメリットとデメリット

深層的な意見や感情の解析が可能
定性調査は、インタビューやグループディスカッションを通じて消費者の深層心理や行動の背景を掘り下げることが可能です。
数値では表せない感情や動機、価値観を詳しく理解できるため、潜在的なニーズや新たなアイデアの発見につながります。
柔軟な質問展開が可能で、表面的な情報だけでなく「なぜそう感じるのか」まで掘り下げることができる点が最大のメリットです。
対象者数の制限と主観に影響されやすい
対象者が少人数であるため、結果を全体に一般化しにくい点がデメリットです。また、個人の主観が強く反映されるため、回答に偏りが生じる可能性があります。
インタビュアーのスキルによって結果が左右されやすく、分析には高度な解釈力が必要です。さらに、調査と分析に時間とコストがかかる点も注意すべきポイントです。
活用事例と効果
商品やサービスの潜在的な問題点や改善策の発掘、顧客の心理や体験理解に活用されます。
新商品のコンセプト検証やブランドイメージの評価、顧客の購買動機の深掘りなど、数字だけでは把握できない本音の把握に効果的です。
顧客理解を深めることで、マーケティングや開発の方向性を具体化し、新たな価値創造につながります。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
定量調査と定性調査の使い分け方

調査目的別の適用例
調査目的によって定量調査と定性調査の選択が異なります。市場規模や顧客層の割合を明確に把握したい場合は定量調査が適しています。
一方、顧客の心理や行動の背景、商品評価の深層理由を掘り下げたい時は定性調査が有効です。また、新製品のコンセプト検証や顧客の意見収集で示唆を得る際にも定性調査が使われます。
両者を目的に応じて使い分けることが成果を左右します。
定量調査・定性調査の組み合わせ方法
効果的な調査では、まず定性調査で仮説や問題点を発見し、その後定量調査でデータを多数取得して仮説の検証を行います。
たとえば、新商品アイデアの反応を少人数のインタビューで検討し、その結果を基に大規模アンケートで市場のニーズや受容度を数値化します。
この段階的なアプローチにより、深い理解と広範な裏付けの両立が可能です。
調査設計の注意点
調査設計では、目的を明確化し、対象者や質問内容の整合性を重視します。
定量調査では、回答が偏らないよう質問文の設計や選択肢のバランス、サンプルの代表性に注意が必要です。
定性調査では、インタビュアーの質問技術や応答の記録の質が結果に大きく影響します。
両者で得られたデータの整合性を意識し、結果の分析と解釈にバイアスが入らないよう配慮することが重要です。
▼以下の資料は、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較した資料です。ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。 類似サービスの比較を行いたい方は、ぜひ参考にしてください。
企業が調査ツールを選ぶ際のポイント

導入目的と調査手法の整合性
ツール選びの基本は、自社の調査目的に合った手法を選ぶことです。
例えば、市場の全体傾向を把握したい場合は定量調査、顧客の深い意見や感情を知るためには定性調査が適しています。
目的と手法の一致が、効果的な調査結果を得るための第一歩です。
ツール機能と操作性の比較
ツールの機能は、自社が必要とする調査内容に応じて選びましょう。
操作性(UIや操作性の良さ)も重要で、使いにくいツールは導入後の運用が難しくなり、時間やコストのムダにつながります。
デモ版やトライアルを活用して、直感的な操作や必要な機能が備わっているかを確認することが重要です。
コストとサポート体制
コスト面では、ツールの初期費用、月額料金、追加費用などを比較し、長期的に無理のないプランを選びましょう。また、サポート体制が充実しているかも重要です。
問い合わせ対応やトラブル時のサポートが迅速かつ丁寧であれば、導入後の運用トラブルや学習曲線を最小限に抑えやすくなるため、検討時には必ず確認しましょう。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。
定量調査や定性調査には、インタビューズのヒアリングツールがおすすめ
インタビューズのヒアリングツールは、アンケートや診断コンテンツを簡単に作成し、ユーザーからのフィードバックを効率的に収集するためのノーコードSaaSツールです。
インタビューズのヒアリングツールは、定量調査や定性調査の両方において非常に有用です。以下に、その理由を解説します。
1.直感的で使いやすい
インタビューズのヒアリングツールは、ユーザーインターフェースが直感的で使いやすく、専門的な知識がなくても簡単に操作できます。これにより、調査の準備や実施がスムーズに行えます。
2.カスタマイズ性が高い
配色やデザインを自由に選べるため、ブランドイメージに合わせたアンケートやヒアリングフォームを作成できます。これにより、調査対象者に対して一貫したブランド体験を提供できます。
3.外部ツールとの連携が容易
Google AnalyticsやSlack、Salesforceなどの外部ツールと簡単に連携できるため、既存の分析ツールと併用してデータを効果的に活用できます。
4.高い回答率に期待できる
インタビューズのヒアリングツールは、回答者が答えやすい設計になっており、高い回答率が期待できます。これにより、より多くのデータを収集し、信頼性の高い結果を得ることができます。
5.コストを削減できる
オンラインでの調査が可能なため、紙媒体や対面での調査に比べてコストを大幅に削減できます。特に大規模な調査を行う場合には、コストパフォーマンスが非常に高いです。
6.14日間の無料トライアル
インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。
▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。
フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。
ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。