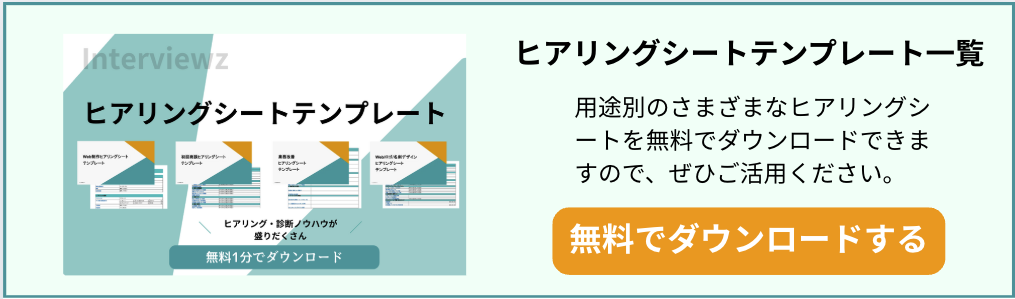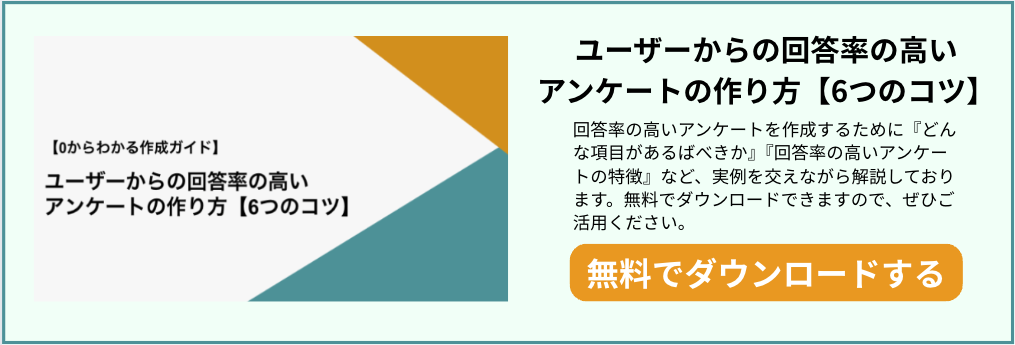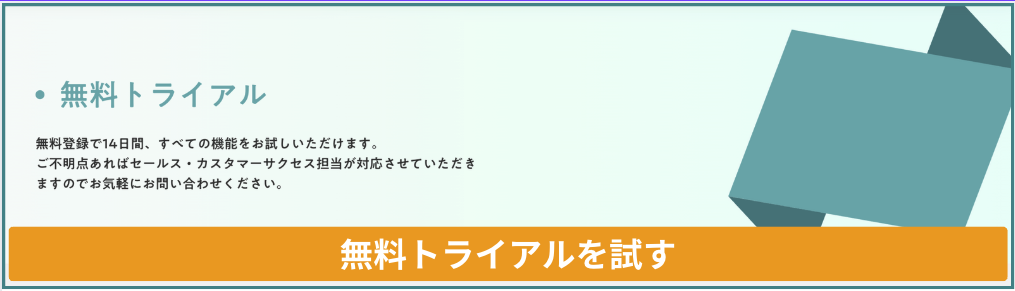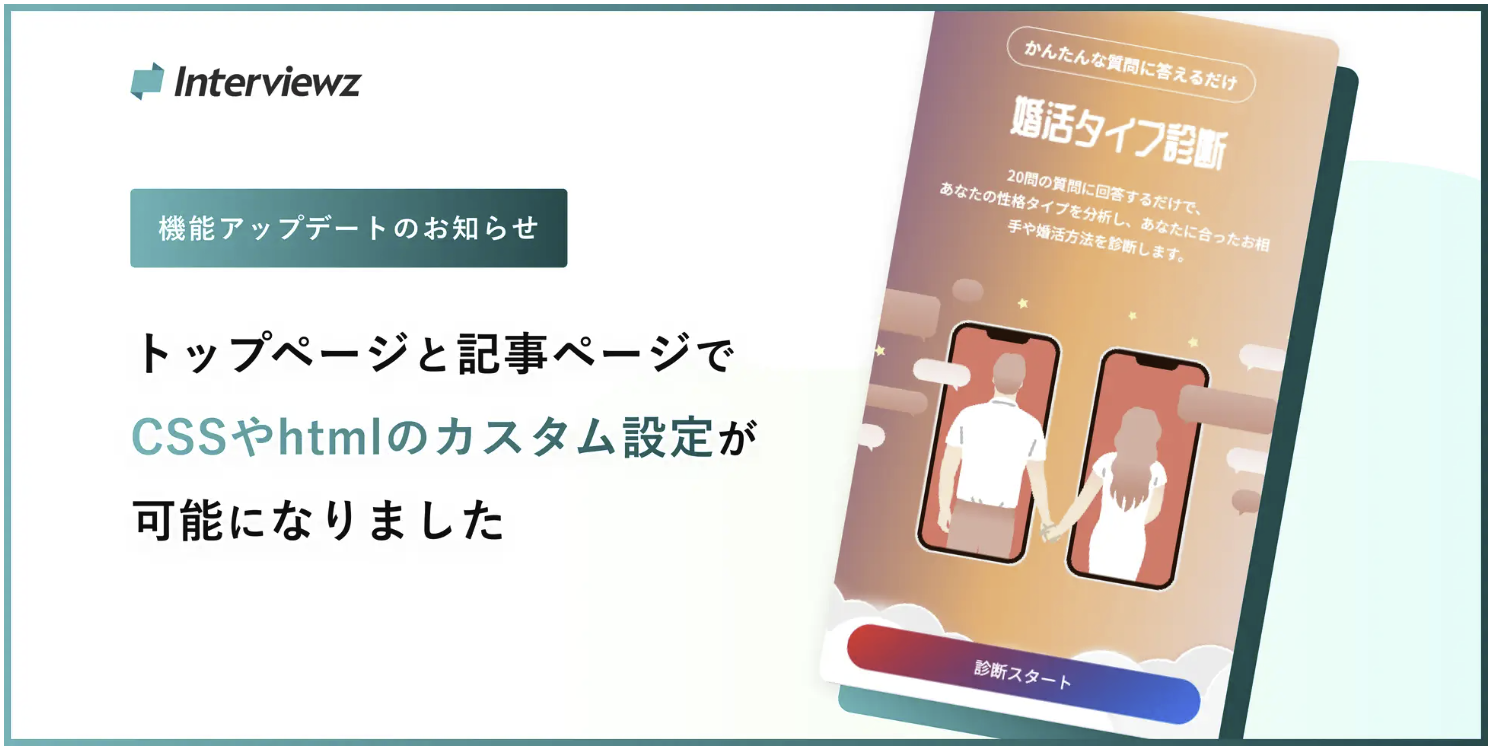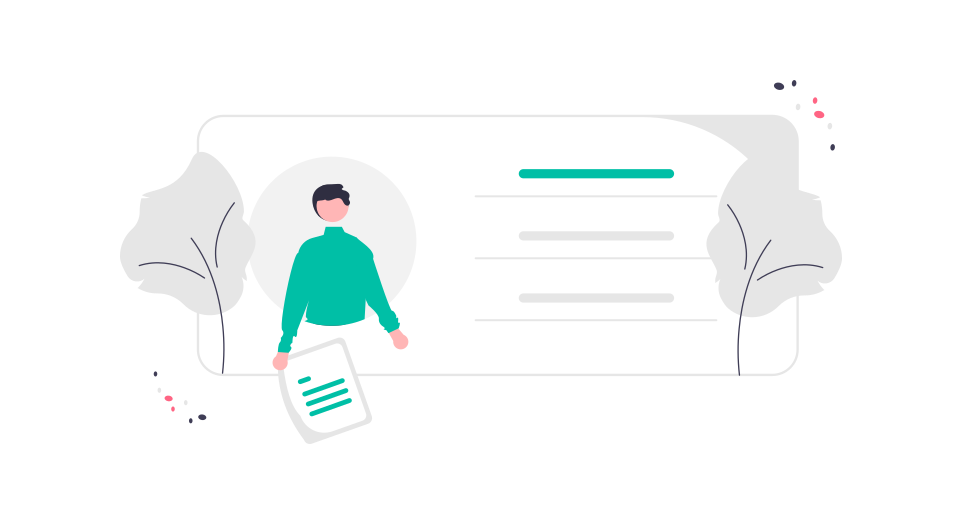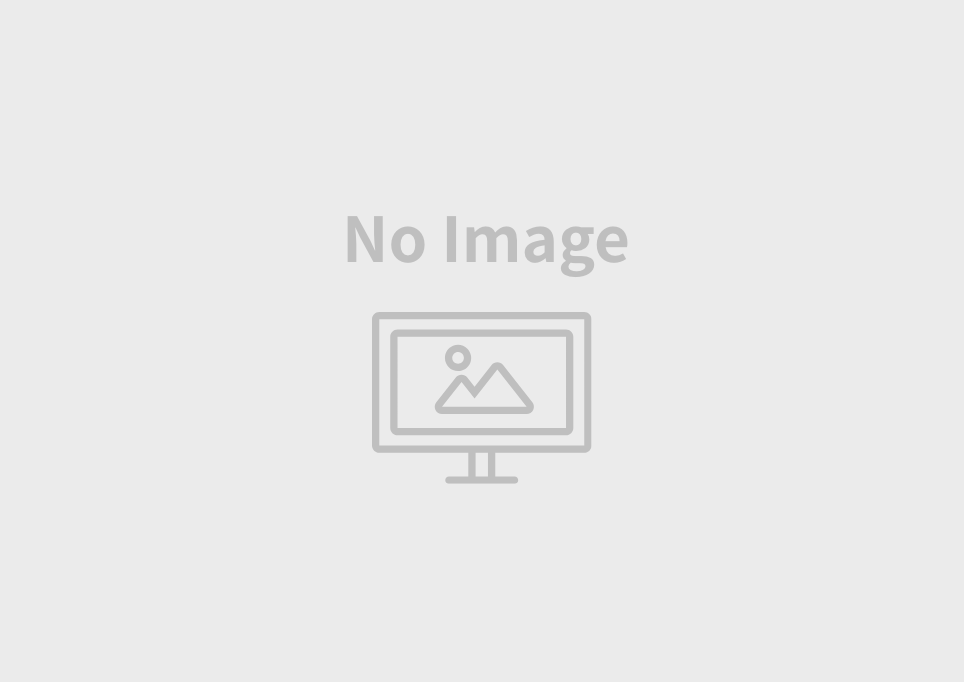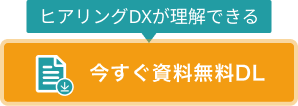インタビュー調査の主な分析方法4つ|資料作成のコツと注意点も解説
- 2025/07/25
- 2025/10/31

目次
インタビュー調査の分析は、集めた情報を価値ある知見へと昇華させる重要なプロセスです。しかし、膨大な発言やデータを前に、どのように整理し、分析すればよいかとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
コーディングやKJ法などの手法を用いることで、発言のパターンやテーマを明確にし、客観的な資料作成につなげることができます。
インタビュー調査では、分析の質が調査全体の成果を左右するため、正しい手順や注意点を押さえることが欠かせません。
そこで今回は、インタビュー調査の主な分析方法4つと資料作成のコツや注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
インタビュー調査の分析とは?基本的な考え方と重要性を解説

インタビュー調査における分析の定義と目的
インタビュー調査の分析とは、インタビューを実施した対象者から得られた自由回答や発言内容を体系的に整理・分類し、そこから意味のあるパターンやインサイト(本質的な気づき)を抽出するプロセスを指します。
主な目的は、仮説の構築・検証、顧客やユーザーの深層心理や行動理由の把握、潜在ニーズや課題の発見などです。
定量調査との分析の違いとメリット・デメリット
インタビュー調査(定性調査)は、数値化できない言語情報や感情、行動理由などの質的データを扱うのが特徴です。
一方、定量調査(アンケートなど)は数値や割合で全体の傾向を把握できるために客観性や比較性に優れていますが、背景や理由までは深掘りできません。
|
分析手法 |
メリット |
デメリット |
|
インタビュー調査 |
|
|
|
定量調査 |
|
|
分析が調査成功の鍵となる理由
インタビュー調査の本質は、表面的な発言だけでなく、その背後にある本音やインサイトを導き出すことにあります。
的確な分析を行うことで、顧客自身も気づいていない潜在的な課題や新たな価値を発見でき、調査結果を実際の施策や商品・サービスの改善に結びつけることが可能です。
ただし、分析が不十分だと得られた情報が活用されず、調査の意義が薄れてしまうため、十分な注意が必要です。
主観的な印象から客観的な洞察への変換プロセス
インタビューの発言録には、個々の主観的な意見や感情が多く含まれます。そこで、これらをコーディングやKJ法などの分析手法でカテゴリー分けし、複数人の発言に共通するパターンやテーマを抽出するプロセスが欠かせません。
このプロセスを経ることで、個別の印象やエピソードを客観的な洞察や実用的な示唆への変換が可能となります。分析の過程では、複数の分析者で視点を共有し、バイアスを排除する工夫も重要です。
このように、インタビュー調査の分析は、数値化できない「なぜ?」に迫るための重要なプロセスです。主観的な発言を体系的に整理し、客観的なインサイトに昇華させることで、ビジネスや研究に活かせる有効な知見を生み出します。
▼ビジネスにおいて「ヒアリングの質」は、その後の提案の精度や成果を大きく左右します。しかし、実際の現場では以下のような悩みがよく聞かれます。
- 「何をどこまで聞けばいいのかわからない」
- 「毎回ヒアリングの内容が属人化していて、標準化できない」
- 「新人や外注メンバーにヒアリング業務を任せにくい」
- 「案件ごとに内容が違うため、毎回シートをゼロから作ってしまう」
下記のヒアリングシートテンプレートでは、上記のような現場の課題を解決するためにWeb制作・採用・営業・ブランディングなど、用途別・目的別にヒアリング項目が体系立てられており、誰でもすぐに使えるフォーマットになっています。
さらに、テンプレートには診断ノウハウやチェック項目も付属していますので、ヒアリングを通じて「課題の構造化」や「次のアクション提案」まで自然に導けます。
無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
インタビュー調査の主な分析方法4つを徹底解説

【方法1】コーディング(コード化)による分析
コーディングではまず、インタビューの発言や回答を「意味ごと」にラベル(=コード)をつけて分類します。
例えば「使いにくい」「便利だった」「価格が高い」など、似た内容をまとめてグループ化します。
このように、多数の意見を整理することで、「どんな意見が多いか」「どんな傾向があるか」を見つけやすくなります。
【方法2】KJ法を活用したグルーピング分析
KJ法では、発言やアイデアを1枚ずつカードや付箋に書き出し、似ているもの同士をグループにまとめます。
机の上で付箋を並べ替えて、「この意見とこの意見は同じグループ」と分けていく作業です。
このように、一見するとバラバラだった意見をまとめることで、全体像や本質的な課題が見つかります。また、KJ法はチームでの話し合いの手法にも向いており、おすすめです。
【方法3】テーマ分析(テーマティック・アナリシス)
テーマ分析では、インタビュー全体を読み込みながら、「何度も出てくる話題」や「共通する主なテーマ」を探します。
その中で、「多くの人が“サポートが親切”と答えている」「“価格への不満”がよく出てくる」など、繰り返し登場する話題をピックアップします。
これらのデータから自然に生まれる“本質的なテーマ”を見つけることで、ユーザーの本音やニーズを深く理解する手法です。
【方法4】内容分析(コンテンツ・アナリシス)
内容分析では、インタビューの発言を単語やフレーズごとに分けて、「どの言葉がどれくらい多いか」を数えたり、特徴を数値で示します。
そして、「“使いやすい”が10回、“高い”が5回出てきた」など、出現回数を集計して傾向を見ます。
内容分析は、多くのデータを客観的に分析できるため、グラフや表で結果を示したいときに便利な手法です。
分析方法の選び方と使い分けのポイント
|
方法名 |
向いている場面 |
特徴 |
|
コーディング |
意見を整理したい・傾向を知りたい時 |
分類・集計がしやすい |
|
KJ法 |
複雑な意見をまとめたい・全体像を見たい時 |
チームでの議論や可視化に強い |
|
テーマ分析 |
よく出る話題や本質を見つけたい時 |
潜在的なニーズや課題の発見 |
|
内容分析 |
データ量が多い・数値で傾向を示したい時 |
客観的な頻度・傾向分析が得意 |
上記のどの方法も「たくさんの意見や発言を整理して、重要なポイントや傾向を見つける」ためのものです。目的やデータの量、チームの状況に合わせて使い分けると、インタビュー調査の結果をより分かりやすく、実践的に活用できます。
インタビュー調査の分析手順と流れ

【STEP1】録音データの書き起こし(文字起こし)
まずは、インタビューで録音した音声データをテキスト(文字起こし)に変換しましょう。
文字起こしは正確さが重要です。また、発言者ごとに分けて記録することで、後の分析がしやすくなります。
音声認識ソフトや自動文字起こしツールを活用すると、作業効率が大幅に向上するためおすすめです。
【STEP2】発言内容の整理とデータ化
次に、書き起こしたテキストを質問ごと・発言者ごとに整理し、Excelや分析シートにまとめましょう。
重要な発言や印象的なエピソードにはマーカーやコメントを付けておくと、後の分析がスムーズです。
データ化の際は、発言の文脈や非言語情報(表情・トーンなど)も補足しておくと深い分析が可能となります。
【STEP3】キーワード抽出と意味づけ
上記で整理したテキストデータから、頻出するキーワードや重要なフレーズを抽出しましょう。
それぞれのキーワードがどのような意味や背景を持つかを整理し、発言の意図や感情を読み取ります。
自然言語処理ツールやテキストマイニングツールを使うと、効率的にキーワードを抽出可能です。
【STEP4】グルーピングとパターン分析
抽出したキーワードや発言内容をテーマやカテゴリごとにグルーピングします(コーディング、KJ法など)。
そして、グループごとに共通点や傾向、相違点を比較分析し、複数の参加者に共通するパターンや特徴的な意見を明らかにします。
図解やマッピングを活用すると、全体像や構造が可視化され、チームでの共有も容易です。
【STEP5】インサイトの導出と仮説検証
最後に、グルーピングした結果から、調査目的や仮説に対する本質的な気づき(インサイト)を導き出します。
例えば「多くのユーザーが○○に不満を感じている」「△△な場面で利用されやすい」など、具体的な示唆や仮説を明確にします。
必要に応じて、他のデータや定量調査結果と照合し、仮説の妥当性を検証することも重要です。
分析を効率化するツールと診断コンテンツの活用
上記のように、文字起こし支援ツール(例:AI文字起こしサービス、音声認識アプリ)を使うことで、録音データのテキスト化が迅速に行えます。
また、テキストマイニングツールや自然言語処理ソフトを活用すると、キーワード抽出や頻度分析、感情分析も自動化できます。
さらに、グルーピングやKJ法支援ツール(オンライン付箋アプリなど)は、チームでの共同分析やワークショップに便利です。
ビジネスなどでより効率的にインタビューを実施・分析する必要がある場合は、インタビューズが提供する診断コンテンツやヒアリングツールを積極的に活用しましょう。データの自動集計・可視化、外部ツールとの連携、セキュリティ管理まで一元化でき、インタビュー調査の設計から分析・活用までを大幅に効率化できます。
効果的な資料作成のコツと構成のポイント

分析結果をまとめる基本的な資料構成
インタビュー調査の資料は、以下の流れで構成すると分かりやすくなります。
- 調査目的・背景(なぜ調査したか、仮説や課題)
- 調査方法(対象者、実施内容、質問設計など)
- 主な発見・要約(結論や重要な気づきのまとめ)
- 詳細な分析(質問ごとやテーマごとの発言傾向・分析内容)
- 発言録・引用(根拠となる具体的な発言やエピソード)
- 結論・提言(次のアクションや施策案)
説得力のある報告書の作成方法
報告書は、論理的な構成(目的→背景→分析→結論→提言)で、読み手がストレスなく理解できる流れにしましょう。
主張と根拠(発言内容やデータ)を必ずセットで示すことで、納得感と信頼性が高まります。
また、冗長な部分は要約し、重要なポイントを強調することが大切です。
発言内容の引用と可視化テクニック
報告書では、発言録や具体的なコメントをそのまま引用し、分析結果の裏付けとして活用しましょう。
また、グラフ、図表、チャート、イラストを活用して、複数人の傾向や共通点・相違点を直感的に伝えることも重要です。
KJ法や上位下位関係分析などの図解も有効な手法となります。
ステークホルダー(企業の利害関係者)に響く報告書の書き方
自社のステークホルダーに対して報告書を作成する際は、調査目的やビジネス課題と直接結びつけて示唆を述べることで、実務担当者や意思決定者に響きやすくなるでしょう。
また、次のアクションや具体的な改善提案まで盛り込むと、報告書の価値が高まります。
社外の関係者に向けた報告書を作成する際は、専門用語や難解な表現は避け、誰でも理解できる平易な言葉でまとめることも重要です。
PowerPointとExcelを活用した資料作成術
Excelで集計・グラフ化したデータをPowerPointに貼り付けて、ビジュアル重視のスライド資料を作成します。
PowerPointでは1スライド1メッセージを意識し、要点を短く明確にしましょう。
Excelの一覧表やクロス集計表は、詳細データや裏付け資料として添付すると説得力が増すためおすすめです。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
インタビュー調査分析の注意点と陥りがちなミス

主観的な解釈に陥らないための注意点
インタビュー分析では、分析者の主観や先入観が結果に影響しやすい点が大きなリスクです。
例えば「これは不満の表れだ」と短絡的に判断すると、客観性が損なわれます。中立的な質問設計や、誘導的でないオープンクエスチョンの活用、複数人による相互レビュー(ピアレビュー)を導入し、主観の介入を最小限に抑えることが重要です。
また、録音・文字起こしを活用して事実ベースで評価する習慣も有効です。
都合の良い結果だけを抜き出すバイアスの回避
研究者バイアス(確証バイアス)は、仮説や期待に合致するデータだけを強調し、都合の悪いデータを無視することから生じます。
そこで、得られたデータをすべて検討し、仮説に合わない意見や少数派の発言も公平に扱うことが大切です。
自由回答形式や多様な設問を用意し、複数人でのデータレビューやセカンドオピニオンを取り入れることで、バイアスを減らせます。
発言の背景や文脈を見逃さないコツ
発言をそのまま受け取るだけでなく、なぜその言葉が出たのか、どんな状況や体験が背景にあるのかを深掘りすることが重要です。
例えば「商品Aが使いづらかったので他人に譲った」という発言も、以前の経験や周囲の状況など背景まで考察することで、分析結果に深みが出ます。
フォローアップ質問や追加ヒアリングで文脈を補足し、背景を意識した分析を心がけましょう。
分析結果の妥当性と信頼性の確認方法
分析結果の妥当性と信頼性の確認する方法は以下の通りです。
- 分析の手順や論理を可視化し、再現性を高める(どのようにコーディング・グルーピングしたかを記録する)
- 複数人での分析・レビュー(ピアレビュー)を実施し、解釈の偏りを検証する
- 仮説に合わないデータや異なる意見も必ず報告書に盛り込む
- 発言録や具体的な引用を根拠として明示する
これらの工夫で、分析の透明性と客観性が担保されます。
チーム内での分析結果の検証プロセス
チーム内で分析結果を検証する際は、次のプロセスを踏むことが大切です。
- 複数人で同じデータを分析し、解釈や分類の違いを議論する
- ピアレビューやワークショップ形式で、仮説や示唆の妥当性を確認する
- 分析手順や判断基準を文書化し、全員で共有する
- 異なる視点や専門性を持つメンバーの意見も取り入れる
このようなプロセスを通じて、主観やバイアスを排除し、より信頼性の高い分析結果を得ることが可能です。
上記のように、インタビュー調査の分析では主観やバイアスに注意し、発言の背景や文脈を深く読み取ることが重要です。複数人によるレビューや手順の可視化を徹底し、妥当性・信頼性の高い分析を目指しましょう。
▼下記の資料では、実際にアンケートを作成する際に回答率の高いアンケートを作成するために『どんな項目があるばべきか』『回答率の高いアンケートの特徴』など、実例を交えながら解説しいます。
アンケート作成でお悩みのある方は、下記の資料を参考にしながら効果的ななアンケートの作成方法を確認してみてください。
【実践編】分析から施策立案までの活用方法

インタビュー分析結果をビジネス施策に活かす方法
インタビュー調査で得られた顧客の声や行動パターンをもとに、マーケティング戦略やWeb施策、商品・サービスの改善案へと具体的に落とし込むことが重要です。
例えば、ユーザーの関心や課題をもとにターゲティングやプロモーション方法を見直したり、Webサイトの情報設計や要件定義に反映させます。
顧客の生の声を整理し、ターゲットが共有する価値観や期待を明確にすることで、説得力ある施策を立案できます。
新商品開発・サービス改善への活用事例
新製品発売前にユーザーインタビューを実施し、ユーザーが新商品に抱く印象や期待、使い方の実態を把握しましょう。これをもとに製品仕様やサービス内容を調整し、発売後のミスマッチやクレームを未然に防いだ事例があります。
また、SaaSサービスでインタビューを通じて利用時の課題や不満点を抽出し、機能改善やサポート体制の強化につなげることで、チャーンレート低下や顧客満足度向上を実現したケースもあります。
顧客理解を深めるための継続的な分析手法
インタビュー調査は一度きりで終わらせず、定期的に実施し、顧客像やニーズの変化を継続的に把握することが大切です。
調査ごとに質問内容や分析手法を見直し、ターゲットのインサイトや価値観の変化を追跡しましょう。
このような継続的な分析により、事業戦略や商品開発の方向性を常に最適化できます。
定量調査との組み合わせによる効果最大化
インタビューによる定性データで得た仮説やインサイトを、アンケートなどの定量調査で検証・裏付けることで、施策の説得力と精度が格段に高まります。
例えば、インタビューで見つけた課題やニーズをもとにアンケート項目を設計し、多数のユーザーに傾向を確認することで、全体傾向と個別事例の両面から施策を強化できます。
上記のように、インタビュー調査の分析結果をビジネスに活用する際は、顧客の声を戦略や開発に落とし込むこと、継続的な分析で変化を追い続けること、定量調査と組み合わせて根拠を強化することが成功のポイントです。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。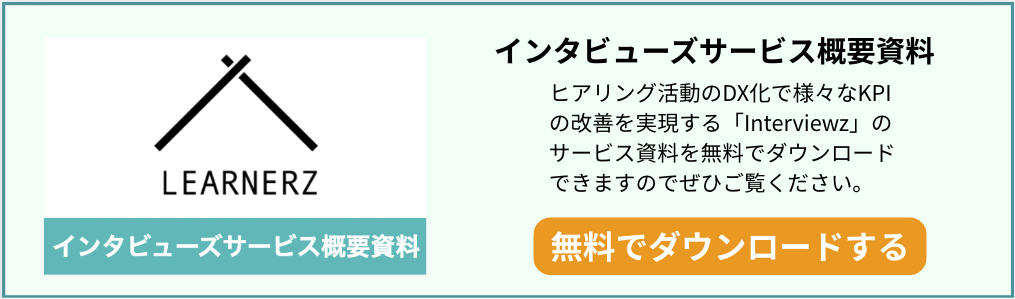
インタビュー調査と分析はインタビューズにおまかせ!
インタビュー調査と分析に、インタビューズのヒアリングツールをおすすめする最大の理由は、その圧倒的な効率性と高い柔軟性、そしてビジネス成果への直結力にあります。
インタビューズはノーコードSaaSサービスとして、タイピングを最小限に抑えた直感的なヒアリング体験を提供し、ユーザーに合わせた情報収集を最短1日で設計可能です。Webやアプリ、メール、チャットなど多様なチャネルに対応し、Salesforceやスプレッドシートなど外部ツールとも即時連携できます。これにより、ヒアリングコストは最大90%削減、問い合わせ数は268%改善、サポート対応時間も半減するなど、実績も豊富です。
さらに、要件定義から定着化まで専門知見でサポートし、分析データをそのままビジネス施策に活かせる点も強みです。
このように、インタビュー調査の設計・実施・分析・活用まで一気通貫で支援できるのがインタビューズの最大の魅力といえるでしょう。
インタビューズは「効率化」「精度」「使いやすさ」「データ活用」のすべてを両立し、調査と分析の成果を最大化できるプラットフォームです。調査担当者の負担を劇的に減らし、ビジネスの意思決定を加速させたいなら、インタビューズの導入がおすすめです。
インタビューズのヒアリングツールは、アンケート調査の分析や効率化に最適です。また、インタビューズでは、14日間の無料トライアル期間でも全ての機能を利用可能ですので、ぜひこの機会にお試しください。
▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。
フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。
ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。