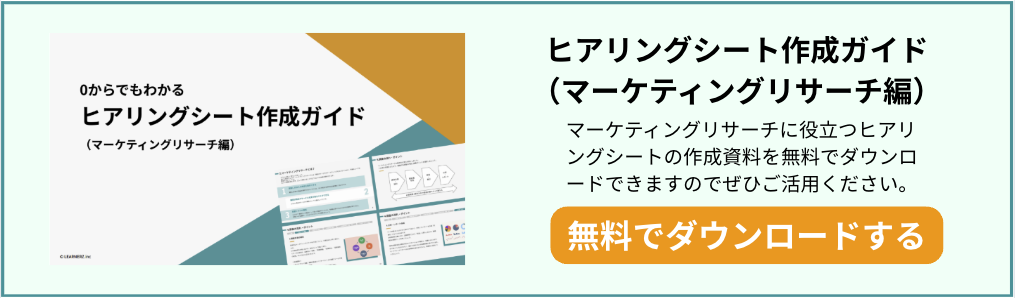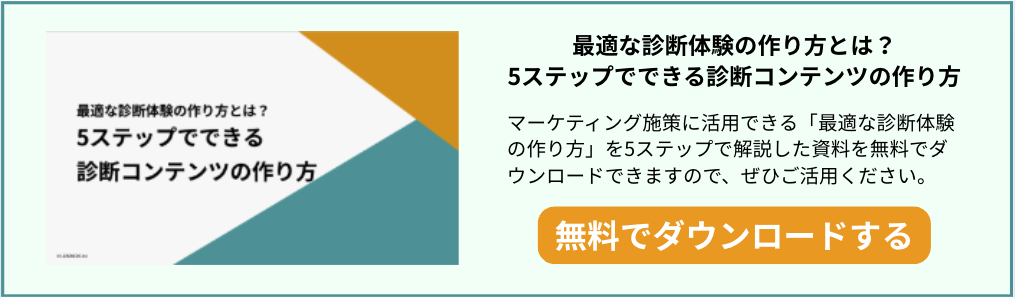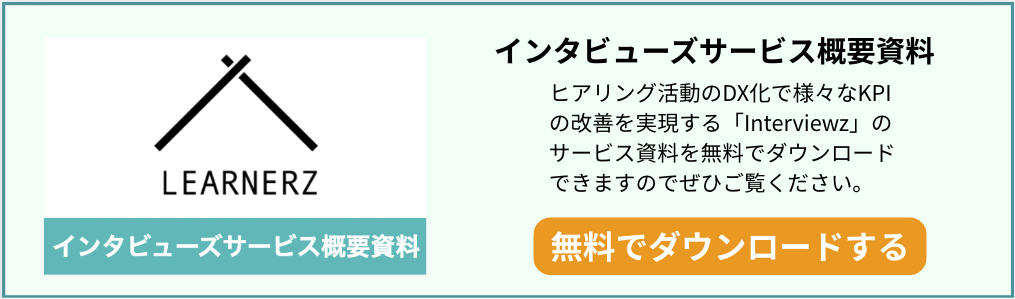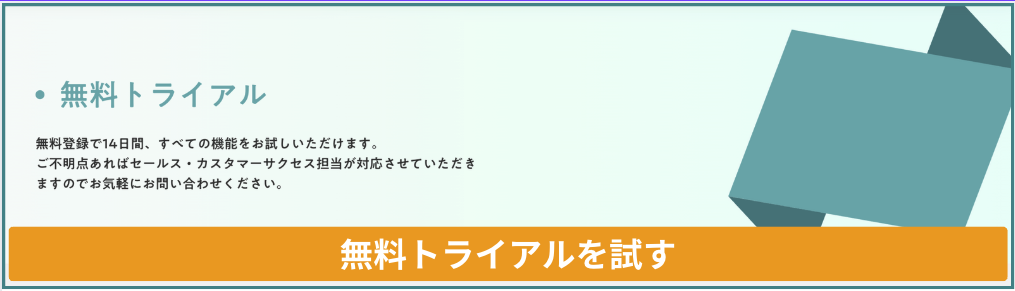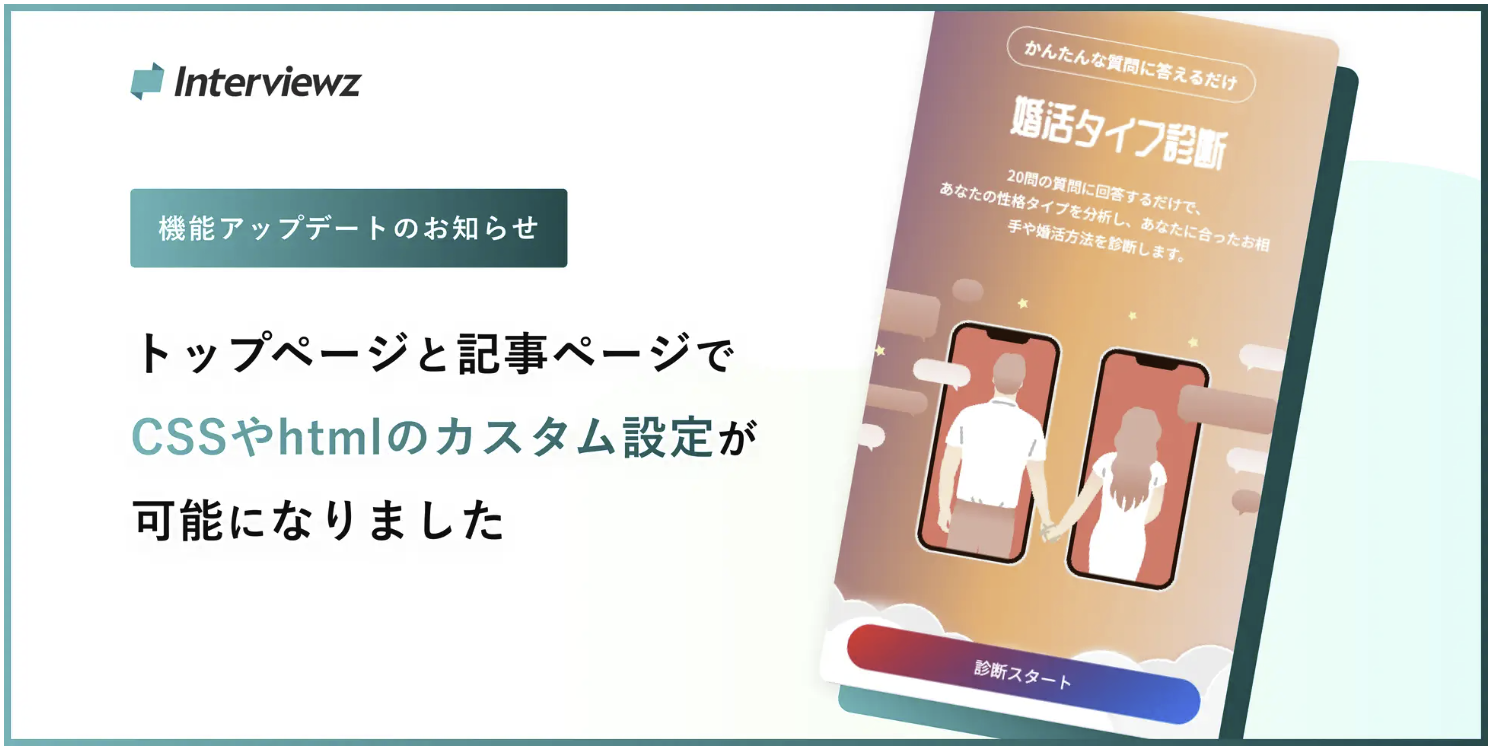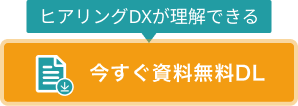顧客分析のフレームワーク7つと効果的な進め方|診断ツールのメリットや活用法も解説
- 2025/09/27
- 2025/09/27
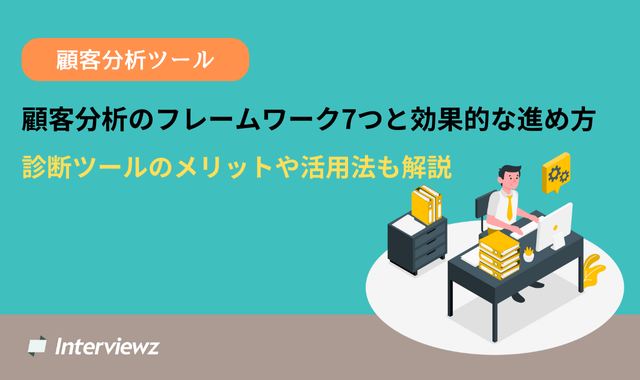
目次
顧客分析はデータを整理し、ニーズを理解して事業成長につなげるための欠かせない取り組みです。
フレームワークを活用することで分析手順が明確になり、戦略策定や施策立案に役立つことが多いです。
さらに診断ツールを組み合わせることで顧客の行動や意識をより深く把握でき、実践的な改善につながる点が大きな強みとなります。
そこで今回は、顧客分析のフレームワーク7つと効果的な進め方、診断ツールのメリットや活用法についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
顧客分析とは?目的と重要性も解説

顧客分析とは、顧客の属性や行動、購買動機、ニーズを整理し、企業の戦略づくりに活かす作業のことです。単に売上の数字を追うだけでなく、なぜその顧客が商品を選ぶのか、どの接点で迷いが生まれるのかを解き明かす作業を含みます。
顧客分析の目的は、次の3つに大きく分けられます。
第一に市場機会の発見です。新しい需要や未満足のニーズを見つけ、適切な価値 proposition(提供価値)を設計します。
第二に顧客体験の改善です。購買プロセスの各段階での障害を取り除き、スムーズな導線づくりを進めます。
第三に長期的な関係構築です。顧客の生涯価値を最大化し、リピート購入や推奨を促す仕組みを作ります。
現代の競争環境では、データと声を結びつけることが重要です。顧客の声を定量データと定性データの双方で捉えることで、施策の効果を確実に高められます。
顧客分析の基本的な意味
顧客分析は、顧客の「誰か」「何を求めているのか」「どういう時に購買に至るのか」を整理する作業です。
データは年齢層や居住地域、購買頻度、利用時間帯などの定量情報と、購買理由や不満点といった定性情報の両方を含みます。定量データだけでは見えない、顧客が感じる価値の優先順位や感情の動きも把握することがポイントです。現場の声を反映させるためには、
インタビューズのようなヒアリングツールを活用して、顧客の本音を自然な形で引き出すことが有効です。
マーケティングにおける顧客分析の役割
顧客分析は、マーケティング戦略の「方向性」と「実行の根拠」を決める羅針盤です。
市場の規模感や成長性を把握し、どのセグメントを狙うべきかを判断します。さらに、広告の訴求点やクリエイティブの方向性、チャネル選択を具体化します。
顧客の声を基にしたペルソナ設計やカスタマージャーニーの可視化は、複雑な購買プロセスを整理し、最適な接点設計を可能にする重要なポイントです。
インタビューズの診断機能を使えば、インタビュー録音の要点を自動で整理し、データと声の両面から施策を導く作業を効率化できます。
戦略立案に顧客データを活かすメリット
顧客データを戦略に活かすと、以下のような効果が期待できます。
意思決定の質が高まる
まず、意思決定の質が高まることです。データと現場の声を統合することで、仮説検証の精度が向上します。
ROI(投資利益率)が改善する
次に、リソースの最適な配分が進む点です。高購買確率の層に重点投資することで、ROIが改善します。
顧客理解が深まり、失敗のリスクが減る
さらに、顧客理解が深まると、商品開発やサービス設計の方向性が明確になり、失敗のリスクを減らすことが可能です。
意思決定の速度と実行力が向上する
最後に、組織内の共通認識が生まれやすくなることもメリットです。部門を跨いだ共有が進み、意思決定の速度と実行力が向上します。
▼下記の資料は、自社のマーケティング戦略の立案を効率化するためのヒアリングシートの作り方をステップ別に解説した資料です。この資料では、マーケティングの課題や調査目的、今回の調査で明らかにしたい事柄を明確にできますので、ぜひご活用ください。
顧客分析に役立つフレームワーク7つと活用事例

顧客分析に役立つフレームワークには、次の7つが挙げられます。
3C分析|市場と競合を把握する基礎フレームワーク
3C分析は、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)を軸に、市場環境を整理する基本手法です。顧客ニーズを正確に捉え、競合の強み・弱み、自社の立ち位置を照らし合わせて、差別化ポイントを明確化します。
活用例としては、新商品開発の企画段階で顧客視点と競合の差別化要素を整理することです。インタビューズを使えば、顧客インサイトを直接収集し、3Cの「顧客」要素を具体的な声として反映できます。
STP分析|ターゲットの明確化から戦略を立てる
STP分析は、Segmentation(市場の区分)、Targeting(狙う対象の設定)、Positioning(市場での位置づけ)の三段階で進めます。市場を細分化して、どのセグメントを狙うかを決め、競合に対して自社が提供する価値を明確化します。
活用例としては、リスティング広告やSNS広告を設計する際に、ターゲット属性を絞り込み訴求軸を整えることです。インタビューズの活用で顧客の購買動機や価値観を深掘りし、セグメント定義の精度を高められます。
ペルソナ設定|理想の顧客像を具体化する
ペルソナは、典型的な顧客像を具体的な人物として描く手法です。年齢、職業、趣味、購買動機、情報収集の行動パターンなどを詳しく設定します。
活用例としては、WebサイトのUI/UX設計で、実在の顧客の視点を前提に導線や表示順を決めることです。インタビューズを用いて得た生の声をペルソナに組み込むと、現実味のある設計が可能となります。
カスタマージャーニーマップ|顧客行動を時系列で可視化する
カスタマージャーニーマップは、認知、検討、購買、利用、継続といった段階ごとに顧客の行動、感情、接点を整理するツールです。接点ごとの課題や改善点を洗い出せます。
活用例としては、展示会やセミナー後のフォロー施策を、接点ごとに「不満・期待・行動」を整理して改善策を設計することです。インタビューズのヒアリングで接点ごとの痛点や期待を直接拾い、ジャーニーの質を高められます。
RFM分析|購買データで顧客をセグメントする
RFM分析は、Recency(最新購買日)、Frequency(購買頻度)、Monetary(購買金額)の3軸で顧客を分類します。RFM分析は、ロイヤル顧客の抽出や休眠顧客の再活性化に有効です。
活用例としては、ECサイトで購入頻度が下がっている顧客に対し再購入を促すキャンペーンを設計することです。インタビューズで顧客の購買行動の背景を理解することで、RFMの解釈をより深く理解できるようになります。
LTV分析|顧客生涯価値を測定する
LTV分析は、顧客が生涯にもたらす利益の総額を見積もり、獲得コストと比較して投資の妥当性を判断する指標です。サブスクリプション型のサービスでは、平均利用年数や解約リスクを見積もり、広告費の適正配分を決定します。
活用例としては、長期的な関係を重視する施策の優先度を決め、解約防止策を強化することです。インタビューズの定性データと定量データを組み合わせると、LTVの推計の根拠がより堅固になります。
コホート分析|顧客グループごとの行動を追跡する
コホート分析は、特定の時期や条件で分けた顧客グループ(コホート)の行動や指標を時系列で比較する方法です。新規顧客と既存顧客の継続率の差やライフサイクルの変化を捉えやすくします。
活用例としては、新規顧客の継続率を改善するための施策を設計する際、改善前後でコホート間の変化を比較することです。インタビューズのデータをコホートごとに紐づけることで、時期依存の声の違いを把握できます。
インタビューズの診断・ヒアリングツールとの連携
各フレームワークを実践する際、入力データの質が成果を大きく左右します。インタビューズの診断・ヒアリングツールを使えば、顧客の声を自動的に整理し、定量データと定性データを統合した情報を効率的に収集できます。
例えばペルソナ設計では、実在の顧客像を支持する具体的な声が集まり、ジャーニーマップの接点ごとの感情変化をより正確に描けます。これにより、LTVやRFMなどの数値分析も現場の声と結びつき、施策の説得力が増します。
▼下記の資料では、自社のマーケティング施策に活用できる最適な『診断体験』の作り方を5つのステップで解説しています。
診断コンテンツはユーザー自身の潜在的なニーズを深掘り、自分が求めるサービスや理想像をより明確にできるため、CVRの向上や診断コンテンツを通じてLTVを向上させることが可能です。
自社のサービスで診断体験を通じたユーザー獲得や認知拡大をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
顧客分析を効果的に進めるステップ

課題設定と目的の明確化
はじめに、解決したい課題と何を達成したいのかを明確にしましょう。目的が曖昧だとデータの取り方や分析の方向性がブレます。
インタビューズを活用して、関係者の関心事や現場の痛点を整理すると、目的設定がスムーズに進みます。
データ収集と整理の方法
定量データと定性データの両方を揃えることが重要です。定量データには購買履歴や行動ログ、定性データにはインタビュー約録音やメモなどが含まれます。
インタビューズを活用したヒアリングをもとに、要点を素早く整理し、分析に使える形に整えましょう。
フレームワークを活かした分析ステップ
各フレームワークの基本プロセスを踏みつつ、データの質を担保しましょう。
例えば3C分析では顧客のニーズを明確化し、競合の強み・弱みと自社の差別化点を結びつけます。STPではセグメントの特性を深掘り、ペルソナやジャーニーに落とし込みます。
結果から具体施策へつなげる活用法
分析結果は、施策の優先順位と実行計画へ落とし込みましょう。LTVやRFMの指標と結びつけると、投資対効果の見通しが立てやすくなります。
インタビューズの声を施策の根拠としてプレゼン資料に活用すると説得力が増します。
▼以下の資料は、ヒアリングに特化した「ヒアリングツール」を10選で比較した資料です。ヒアリングツールは、診断コンテンツの作成やチャットボットなどで、ユーザー情報のヒアリングを行うツールです。 類似サービスの比較を行いたい方は、ぜひ参考にしてください。
顧客分析の注意点とよくある課題

データが属人化して活用できない
特定の担当者だけがデータを握ってしまい、他部門がアクセスできずに分析が孤立するケースが多いです。これでは最新情報が共有されず、意思決定の質が落ちてしまいます。
解決策としては、データガバナンスを整え、部門横断で使える共通データ基盤を整備することが重要です。権限に応じたアクセス権、定期的なデータ更新、標準化されたデータ定義を設定し、インタビューズのようなツールの共有機能を活用してヒアリング結果を全員が閲覧・検索できる状態にしましょう。定期的なデータカレンダーを設定し、誰でも最新情報を参照できる運用を作ると効果的です。
分析が過剰に複雑になりすぎる課題
フレームワークを乱用すると、分析が煩雑になり現場が混乱する可能性が高まります。目的と結びつかない指標が増えると、意思決定の軸がブレてしまいます。
解決策としては、目的を3点程度に絞り、必須指標を最小限に設定するのが有効です。分析の手順書を作成し、1つの課題に対して1つのフレームワークを適用する「絞り込み運用」を徹底しましょう。定性的データは要点だけを抽出して要約表に落とし、定量データと結びつける際は対応表を作成して関係性を可視化します。
調査の負担による回答率の低下
長時間の調査や煩雑な質問設計は顧客の負担となるため、回答率が低下しがちです。結果としてデータの偏りが生じやすくなります。
解決策としては、短時間で完了する設問設計を見直し、インタビューズの自動設問生成機能を活用して核心をつく質問だけに厳選するのが効果的です。また、回答のインセンティブを明示し、重要性と使われ方を伝えることで動機付けを高めましょう。
質の高いサンプルを早期に確保するため、パイロット調査を小規模で実施し、改善しながら本調査へ拡大するのも良い方法です。
定性データの主観性と再現性の不足
インタビューの発言は個人の主観に依存しやすく、解釈にバラつきが出やすいです。統計的な裏付けが不足すると、施策の信頼性が下がります。
解決策として、インタビューズの自動要約・タグ付け機能を使い、定性データを体系化しましょう。複数人で同じデータを評価するコードブックを作成し、評価基準を共有します。定性データと定量データを結びつけるマトリクスを作成し、どの声がどの数値指標に影響したかを明示します。第三者チェック(ペアレビュー)を導入すると、信頼性が高まるためおすすめです。
データと声の整合性が取れず、矛盾した結論になる
お客様の声と購買データが噛み合わず、顧客の価値やニーズの真意が誤解されるケースも少なくありません。
解決策としては、データ統合の設計を見直し、定性データと定量データの結びつき方を明確化する必要があります。例えば、ペルソナ設定時に「声の根拠となる定量指標」をセットで管理し、カスタマージャーニーの各接点に対して「不満・期待・行動」を数値と声で対応づけます。データの整合性を検証するための仮説検証プロセスを設け、矛盾があれば原因を仮説→検証→修正のサイクルで解消するのが効果的です。
▼下記の資料では、ヒアリング活動によってお客様のお問合せやCVRの向上を達成できた実例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
顧客分析を成功させるための活用ポイント

定量と定性データを組み合わせる意味
定量データは購買履歴やアクセス数など、数値で再現性を持つ情報です。一方、定性データは顧客の思考や感情、動機といった言葉の裏側を拾います。両者を組み合わせると、表面的な数字だけでなく「なぜそうなるのか」の理由まで見えるようになります。
例えばRFM分析の結果を、インタビューズの声で補足することで、再購入を促す具体的な価値提案や施策の根拠が強化され、提案の説得力と実行力が高まります。このように、データの統合は、意思決定のリスクを減らし、現場の理解を深めるポイントです。
部門横断での共有と意思決定への活用
顧客分析は部門ごとに見方が偏りがちですが、部門横断で共有することで視点の幅が広がります。マーケティングだけでなく、商品開発・CS・営業などが同じ事実を元に議論することで、施策の整合性が保たれ、実行力が向上します。
インタビューズの声データを共通のプラットフォームで閲覧・分析可能にすれば、定性・定量の両方を共通言語として扱えます。結果として、意思決定の速度と協力体制が強化され、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
継続的分析と改善サイクルの確立
顧客分析を一度実施して終わりではなく、四半期ごとなどの周期で見直すことが重要です。新しいデータを取り込み、仮説を検証し、施策を修正するサイクルを回すと、変化に強い組織になります。
インタビューズを活用して、最新の顧客の声をリアルタイムで反映させると、定性データの鮮度を保てます。KPIを再設定し、成果を測定して次の改善案を立てる循環を作れば、長期的な顧客価値の最大化を実現可能です。
ヒアリングから得たデータをフレームワークに反映する方法
まずは、ヒアリングで得た情報の整理と分類から始めましょう。要点を定性的に抽出し、3C・ペルソナ・ジャーニーなどのフレームワークの要素に落とし込みます。例として、顧客の不満点を「カスタマージャーニーの接点」に対応づけ、STPのセグメント特性と照合します。
インタビューズの自動要約機能やタグ付け機能を活用すれば、声を体系的なデータセットへ変換でき、分析の再現性と共有性を高めることが可能です。このような定性データが分析の核となり、施策設計の実効性が増すのです。
▼Interviewz(インタビューズ)は、ノーコード型のSaaSツールで、顧客ヒアリングの効率化をサポートするために設計された画期的なソリューションです。
インタビューズは、以下の特徴を兼ね備えています。
- 簡単な操作性
タップ操作だけで、診断や質問がスムーズに行えます。技術的な知識がなくても直感的に操作できるので、誰でも簡単に利用できます。
- 多彩な連携機能
SlackやGoogleスプレッドシートなど、外部ツールとの連携が可能です。これにより、データの共有や分析がより効率的になります。
- EFO(入力フォーム最適化)機能
ユーザーの負担を軽減するために、入力フォームを最適化しています。これにより、ストレスなく情報を収集することが可能です。
- マーケティング調査にも対応
カスタマーサポートやアンケート収集、マーケティング調査など、さまざまな場面で活用できる柔軟性を持っています。
上記のように、「インタビューズ」は顧客ニーズを正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実現するために欠かせないツールです。より詳しい情報や導入事例について知りたい場合は、ぜひ下記のサービス概要をご参照ください。
インタビューズの診断・ヒアリングツールで顧客分析を強化するメリット

自動設問生成で情報収集を効率化
インタビューズのツールは自動で設問を生成でき、調査目的に合わせた質問を短時間で準備可能です。これにより、ヒアリング計画の手間が大幅に減り、効率的な情報収集が実現します。
また、設問のバリエーションや条件分岐も自由に設定できるため、対象者ごとに最適な質問を投げかけることで、質の高いデータが得られるでしょう。
顧客の声を数値化と可視化に変える仕組み
集めた顧客の声をテキスト解析やスコアリングで数値化し、ダッシュボードで可視化できます。これにより、感情や満足度の傾向が直感的に理解でき、課題や強みが明確になります。
視覚化されたデータは社内で共有しやすく、具体的な改善施策を導く判断材料としても活用可能です。
フレームワーク連携で分析を容易にする強み
インタビューズは既存の分析フレームワーク(カスタマージャーニーやペルソナ設計など)と連携可能で、収集データを体系的に整理できます。これにより、顧客インサイトの抽出や戦略立案がスムーズになり、分析にかかる工数を削減可能です。
企業にとっては、効率的に市場や顧客理解を深められるのが大きなメリットです。
実務で成果につながる活用事例
ある企業では、インタビューズを活用して顧客の潜在ニーズを発掘し、商品改良や営業施策に反映させて売上増を達成しました。
また、カスタマーサポートの質向上により顧客満足度が上昇し、リピート率向上に寄与しました。
このような具体的な成果が、実務におけるインタビューズの活用価値を証明しています。
インタビューズは14日間のトライアル期間中もすべての機能を無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。
▼Interviewz(インタビューズ)に新機能が追加され、CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込みが可能となりました。これにより、自社ブランドのデザインに合わせた診断・ヒアリングページを最短1日で構築できます。
フォントやカラーの変更、アニメーション追加、外部ツールや分析コードの設置も簡単で、SEO対策やCVR向上、データ活用がスピーディーに行えます。さらに、プレビュー機能で事前確認し即時反映できるため、マーケティング施策の自由度と実行スピードが大幅に向上し、リード獲得や効果測定改善を加速させることが可能です。
ぜひ下記の資料から、インタビューズの詳しい機能をご確認ください。
Interviewz(インタビューズ)をご活用いただくことで以下のことが解決できます。
• 新規お問い合わせ、相談数の向上
• ヒアリングの内容の最適化から受注率の向上
• ヒアリングコスト(人件費・タイムコスト)の削減
• 既存顧客のお問い合わせのセルフ解決(サポートコストの削減)
• サービス/プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客、従業員のエンゲージメント向上
• データ登録負荷の軽減
• サイトにおけるユーザーの行動情報のデータ蓄積

▼Interviewz(インタビューズ)の主な活用方法
• 総合ヒアリングツール
• チャットボット
• アンケートツール
• カスタマーサポートツール
• 社内FAQツール
Interviewzの機能一覧|総合的なヒアリング活動を網羅
Interviewzでは、下記のような総合的なヒアリング活動を支援する機能を揃えております。